
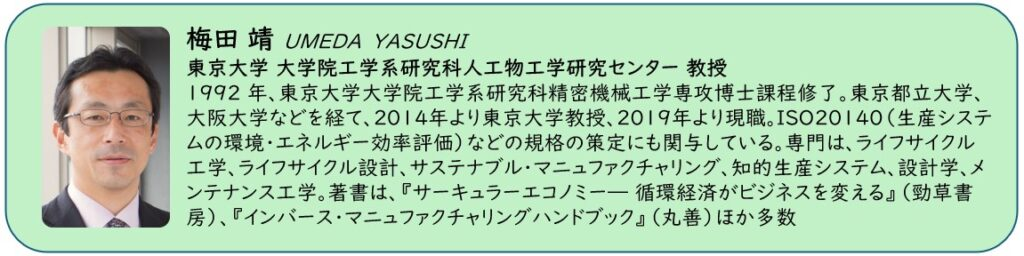
「ロボット自動解体」
デンソーがロボットを使って廃車を自動精緻解体するプロジェクトBlueRebirthを環境省の支援を得て進めていて、これが面白い。
従来の廃自動車処理を簡単に説明すると、自動車から有価物(部品として売れるドアやエンジンなど)と危険物(ガソリン、鉛蓄電池)を取り除いた後、車全体をシュレッダーに投入して、粉々にして、磁石で鉄を取って、アルミや銅も取れるだけ取って、ウレタンなどのプラスチックを中心とした残りはシュレッダーダストとしてサーマルリサイクルする。これだとシュレッダーの中であらゆる破片がごちゃごちゃにかき混ぜられるところからスタートして、そこから材料ごとに選別するのでどうしても純度が下がる。
このBlueRebirthの精緻解体というのは、シュレッダーを使わずに、部品を取り外したり、ボディを切断したりしながら解体する。こうすれば、ぐちゃぐちゃに混ぜることなく素材ごと、たとえば、プラスチックだったらPPやPS、ウレタン。アルミだったら合金の種類ごとのレベルで分けられるので、リサイクル率も上がるし、リサイクル品の品質も上がる。しかし、これを人手でやると「時間がかかって人件費がかさんで、とてもコストに合わないから自動解体で行きましょう」というストーリーである。これは全くもって正しく、うまく行けば拍手喝采である。この連載で何度か触れているが、廃自動車由来のプラスチックを自動車生産に一定割合で使わなければいけないというEUのELV規則(案)への対応ということが、リサイクルプラの需要やコスト負担の面で、今回のプロジェクトの後押しとなっている。
さて、自動解体というのはある種の鬼門であって、筆者がエコデザインに関わり始めた1990年代初頭から延々と研究され続けているテーマであるがほとんど日の目を見ていない。成功例としてあげられるのは、AppleのiPhoneを分解するLianやDaisyぐらいだろうか(検索すればすぐにビデオが見つかります)。これもiPhoneに限定した話だから成り立つのであって、少ない機種、スマホはだいたいキレイだから分解ロボットが使えるのである。それにしても、解体される台数のうちで、実際にロボットで解体される割合はどのくらいであろう? この割合が高いということはまだ使えるものをどんどん解体しているのではという疑念が湧くし、低ければやっぱりデモなのねということになる。
それがBlueRebirthは自動車である。メーカーは多様、車種、年式も多様、多くはボロボロ、サビサビ、リユース部品販売用に部品も抜かれている。こういったさまざまな面での多様性に、繰返し作業を得意とするロボットを含む自動化技術は対応ができないというのが定説ではある。BlueRebirthでは、当面、軽自動車に限定するなど範囲を絞るそうではあるが、その上で、現代的なDXやAIなどの活用でこの問題にどこまで迫れるかが見ものである。想定よりうまく行く部分と、やっぱり限界があるね、という部分の境界線がかなり明確になり、さまざまな課題が見えてくるのではないか。学術的にはこの辺りに興味がある。BlueRebirthでやっているのは、自動精緻解体ラインをつくるに当たって核となるいくつかの自動解体工程の開発であるように見えた。人が行う解体作業を記録し、計算機上で再現、改良して、ロボットで再現して解体するシステム。手術支援用のリモコン操作の双腕ロボットシステムを使って、人がこれを操作して、細かい解体を行い、その作業プロセスを再現して自動解体する、などなど。実際にどういう締結が解体しやすいか、しにくいか、表面処理や不純物をどうやって除去するか、具体的に検討を行っている。
これ以外にも、いろいろ総合的に検討していて、手解体で精緻解体をやって、時間がどの位かかるか、リサイクル性がどの位上がるか、どこが難しいかなどを計測している。実際に百何十台の自動車を解体してデータを取っている。これだけでも充分貴重である。このデータを使ってLCAを行い、精緻解体がシュレッダー方式に比べても大きくCO2排出量を削減する可能性があることを検証している。また、得られたプラスチック、アルミなどを使って再生材、再生部品を作り、自動車に使えるか試している。課題は残っているが、クリティカルな問題はないという結果だったと理解している。さらには、こういった自動解体システムは設備コストが高すぎて、中小の自動車解体業の人達が簡単には導入できそうもない。それならば、リースやPaaSにするのかなどのビジネスモデルの検討も行っている。
BlueRebirthが凄いのは、このプロジェクトを、カーメーカーでもなく、リサイクラーでもなく、Tier1のデンソーがやっているところである。それも、企業を中心に30機関ぐらい巻き込んで大きなコンソーシアムをつくっている。こういうことは誰かが先頭に立たないと進まないという意味で敬意を表したいし、世界最高水準のデンソーの生産技術、自動化技術が一筋縄では行かない解体工程にどこまで通用するのか、というのが大いに見ものである。これがうまく行けば、製品ライフサイクル全体を生産技術的な視点で再構成する大きな突破口になる。循環型製造業の未来の姿を見せてくれている。ちなみに欧州の主体は、PST (Post Shredder Technology)といって、冒頭に述べたシュレッダーにかけた後に、選別技術、分別技術を頑張って、回収する材料の品質を上げようというアプローチである。BlueRebirthの方が筋が良いので何とか頑張って貰いたい。
それと、このプロジェクトには大手のリサイクラーもコアメンバーとして参画しているのだが、話題になるのは、国外流出が止まらなくて国内で処理する廃車の台数が急激に減っているという話である。中古車として輸出されてしまうもの、ヤード業者がスクラップとして輸出してしまうもの(悪くすると、輸出先で2個1でくっつけて走らせる)。これらを止めるのは至難の業。軽自動車は国内のガラパゴス規格なので輸出需要がほとんどない。技術開発が明るい未来を見せてくれている一方で、こういう難しい話が渦巻いている・・・。
この記事は、会員専用記事です。
有料会員になると、会員限定の有料記事もお読みいただけます。


